機械検査学科の勉強その1
しっかりと覚えよう。意味がわからない語句は、インターネットで検索をしてください。答えが出てきます。
○1 目量とは、 目幅に対応する測定量の大きさのことである。
○2 ブロックゲージを複数使用する際、ゲージ面を数回こすり合わせると密着する。これをリンギングという。
×3 ハイトマスタは、基準器であるので、使用前におけるブロックゲージによる寸法校正は必要ない。必要あります。
○4 シリンダゲージは、 内径測定用の比較測定器で測定子の動きをロッドを経てダイヤルゲージで読み取る方式の測定器である。
×5 限界ゲージは、実寸法を正確に測定するために使用される。許容最大寸法と最小寸法の2個のゲージを使用して公差内にあるかを測定する。
○6 外側マイクロメータのラチェットは、測定する圧力を一定に保つためのものである。
○7 マイクロメータ、ノギス等で測定値を読み取るとき、視線が目盛面に直角になるような方向から読み取ることが大切である。
○8 ダイヤルゲージは、単独では測定できないので、保持具が必要である。
○9 日本工業規格(JIS)によれば、サインバーの呼び寸法はローラの中心距離で表す。
○10 ノギスは外側マイクロメータに対してほぼ10倍の総合誤差を持つ。
○11 工具顕微鏡では、ピッチ及び山の角度が測定できる。
×12 サインバーは、マイクロメータの基準ゲージである。基準ゲージではなく、「角度測定」に使われます。
○13 ノギスの外側測定の器差を検査する方法は、 外側用測定面の元及び先にブロックゲ レージを挟んで測定する。
○14 ショア硬さ試験機は、 ロックウェル硬さ試験機に比べ、一般に、測定値のばらつきが大きい。
×15 めねじの有効径は、 ねじリングゲージで検査することができる。できません。
○16 旋盤の主軸中心線と往復台の平行度検査はテストバーとダイヤルゲージを用いて行う。
○17 抜取検査は、一つ一つの品物を保証することはできない。
○18 ロットとは、等しい条件下で生産され、又は生産されたと思われる品物の集まりのことである。
×19 モジュール5、歯数 30枚の平歯車のピッチ円直径は、35mmである。 d=mz+2mより、5×30+2×5=160が正解
○20 ころがり軸受を荷重方向で大別するとラジアル軸受とスラスト軸受に分けられる。
○21 旋盤におけるベッド上の振りとは、ベッドに触れずに主軸に支えることのできるエ作物の最大径のことである。
×22 形削り盤は、テーブルを往復運動させて加工する機械である。テーブルではなく、「刃物」です。
×23 普通旋盤は、刃物が主軸とともに回転し、工作物に送り運動を与えて加工する機械である。 刃物ではなく、「材料」です。
×24 研削といしの粒度46は、粒度24より粗い。粗いではなく、「こまかい」
×25 アルミニウムは、銅より線膨張係数が小さい。小さいではなく、「大きい」
○26 熱処理の焼戻しは、焼入れにより硬化させた鋼にじん性を与えることができる。
○27 日本工業規格(JIS)材料記号においてFCは、ねずみ鋳鉄を示す。
×28 製図法で口10は、直径10mmの丸棒を表す。 □は角材です。
○29 電圧(V)は、抵抗(R)×電流(I)で求められる。V=IXR
×30 精密な作業における作業面の照度は、70ルクス以上が望ましい。→300が正解です。 標準は→150
Copyright c shiozawa commercial and technical highschool all rights reserved
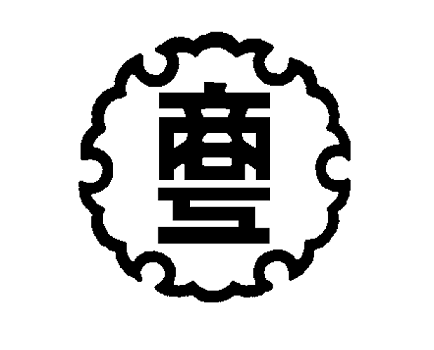 新潟県立塩沢商工高等学校
新潟県立塩沢商工高等学校